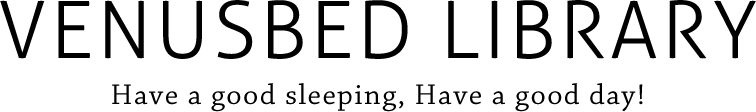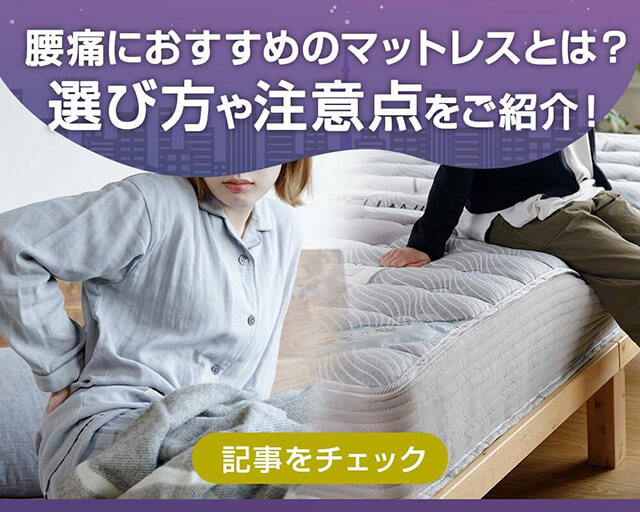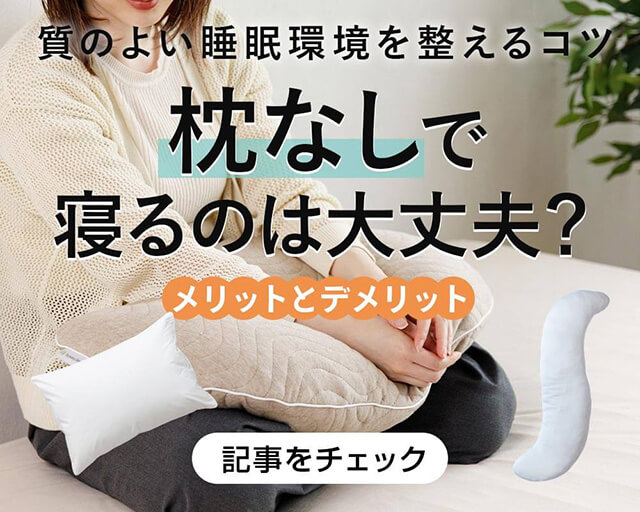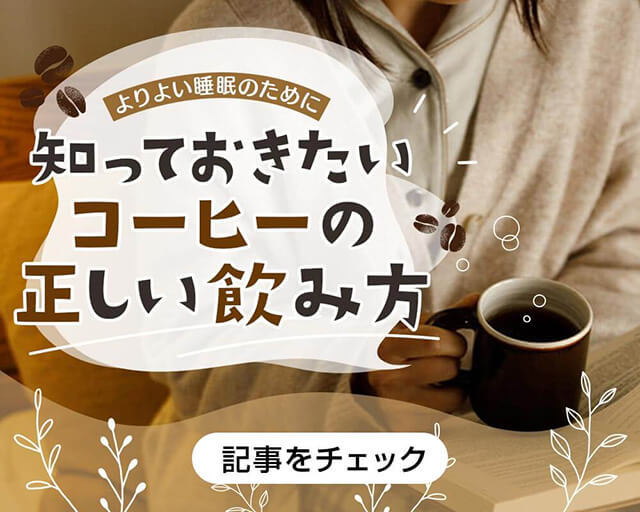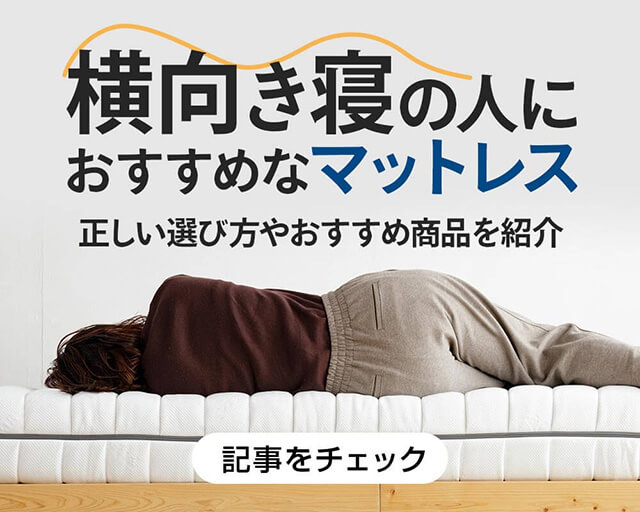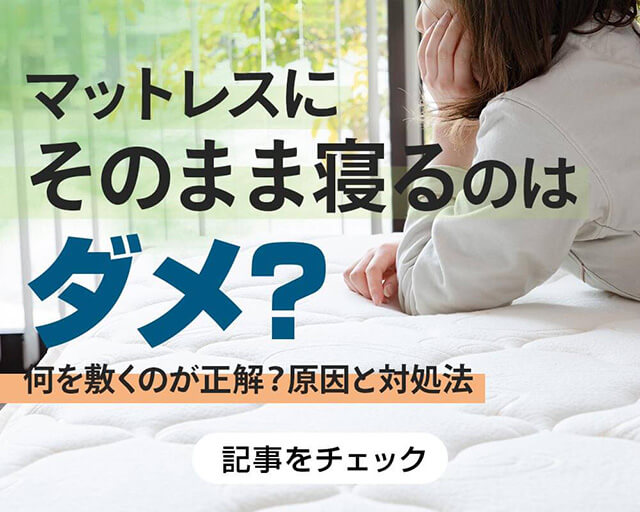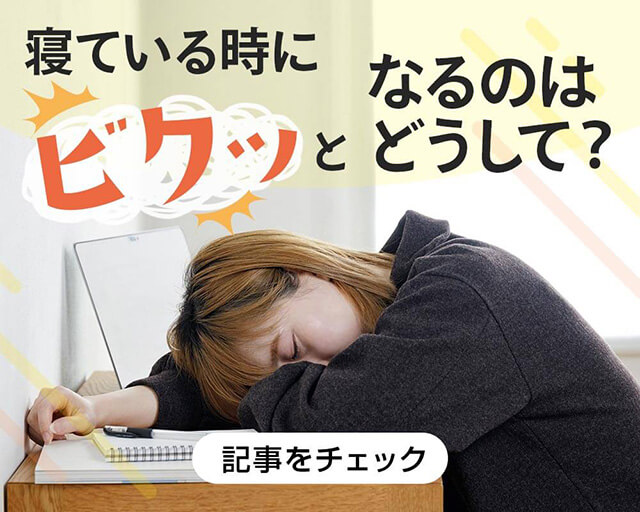耳栓は耳に良くないの?耳栓をつけるメリットとデメリット、正しく使う方法を徹底解説
公開日:2025.01.27
更新日:2025.01.21
気になる騒音をシャットアウトできる耳栓はさまざまなシーンで活躍するアイテムです。手軽に使えて便利ですが、正しく使わないと病気の原因になることもあるため、使い方に注意する必要があります。本記事では、耳栓は耳に良くないのか、耳栓をつけるメリットやデメリット、正しく使う方法を詳しく紹介します。耳栓について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
※当サイトで紹介している商品の中には一部アフィリエイト広告を利用しているものがあります。
耳栓は耳に良くないの?
耳栓は耳に良くないという話を聞いた方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、耳栓の使用で直接的に耳に悪影響が出ることはありません。ただし、正しく使わないと耳を傷つける可能性があります。特に睡眠時に使用する場合は長時間つけたままになるため、使い方に注意が必要です。
耳栓をつけるメリットとは
ここでは、耳栓をつけることによる主な2つのメリットを取り上げて解説します。
就寝時の使用は睡眠の質向上につながる
就寝時に耳栓をつけることで気になる周囲の雑音を大幅にカットできます。基本的に35〜40dB以下の睡眠環境が理想とされており、例えば人の話し声(約50〜61dB)やエアコンの動作音(約41〜59dB)などが聞こえると睡眠の妨げになるおそれがあります。耳栓の使用によって眠りやすくなり、睡眠の質向上につながるのが大きなメリットといえます。

手に入りやすい
ドラッグストアなどで手に入りやすいのも耳栓のメリットです。睡眠時の騒音対策としてリフォームや防音カーテンなどの使用が挙げられますが、コストや時間がかかりやすいものです。その点、耳栓なら購入してすぐに使い始めることができて大変便利です。
耳栓をつけるデメリットとは
耳栓をつけることには、デメリットもあります。ここでは、主な2つのデメリットを取り上げて解説します。
外耳炎になるリスクがある
耳栓をつけることで「外耳炎(外耳道炎)」になるリスクがあると言われています。外耳炎は、耳の通り道(外耳道)や鼓膜の外側にある耳介が傷ついて炎症を起こす病気です。不衛生な状態で使い続けていたり、間違った方法でつけていたりすると発症しやすいため、耳栓を使うときは注意が必要です。
耳に負担がかかる可能性がある
耳栓を長時間使っていると、耳に負担がかかりやすくなります。耳の中に押し込みすぎたり、耳が窮屈に感じるくらいぴったりしていたりすると継続的な刺激になるおそれがあります。つけていても負担を感じないものを使用することが大切です。

【使用目的別】おすすめの耳栓の種類と特徴
ここでは、おすすめの耳栓の種類とその特徴を使用目的別に紹介します。
騒音が気になるときは「フォームタイプ」
雑音で集中できないときは「フォームタイプ」がおすすめです。フォームタイプはスタンダードな耳栓のタイプで、ウレタンフォームが主な素材となっています。指でつぶして耳に入れ、ウレタンフォームの復元力で徐々にふくらませてフィットさせるため、しっかり遮音できるのが特長です。柔らかい肌触りで耳への負担も少なく、睡眠時にも使いやすいでしょう。

騒音のみシャットアウトしたいときは「デジタルタイプ」
騒音のみをシャットアウトしたいなら、ノイズキャンセリング機能つきの「デジタルタイプ」を使うと良いでしょう。デジタルタイプの耳栓の特長は、つけていても呼びかけられる声やアナウンス、着信音などの必要な音は聞き取れることです。そのため、外出中や仕事中でも使いやすいのがメリットです。

砂や埃から守るときは「フランジタイプ」
工事現場などの砂や埃が多い環境で使う場合、「フランジタイプ」がおすすめです。フランジタイプはシリコン素材などの柔らかいヒレ状で、着脱しやすいように軸がついている耳栓です。遮音性はフォームタイプに比べて多少低めですが、耳に入る部分に手を触れずにつけることができて水洗いも可能なため、衛生的に使えます。

水の侵入を防ぎたいときは「防水タイプ」
プールなどで水の侵入を防ぎたいときは「防水タイプ」の耳栓がおすすめです。防水タイプとしては、形状を変えられるシリコン粘土の耳栓があります。耳に入れるのではなく、耳の穴周辺を覆うように使うので異物感や痛みを感じにくいのが特長です。
気圧を調整するなら「飛行機専用耳栓」
飛行機に搭乗中、気圧で耳が痛くなりやすい人には「飛行機専用耳栓」をおすすめします。この耳栓は中心に穴が開いている形状となっており、耳にかかる気圧を軽減して不快感を和らげる効果が期待できます。購入の際は「飛行機用」「気圧コントロール」といったパッケージの記載を確認すると良いでしょう。
使用目的以外で耳栓を選ぶ方法は?
ここでは、耳栓を使用目的以外で選ぶ方法を2つ紹介します。
自分の耳に合いやすい素材・形状を選ぶ
耳栓のつけ心地は人それぞれです。そのため、自分の耳に合いやすい素材や形状で選ぶことがポイントになります。耳栓の主な4つの素材の特徴は下記のとおりです。
| 素材 | メリット | デメリット |
| ウレタン・ポリウレタン | 柔軟性が高く、耳の形状に合わせやすい外部音を効果的に遮断できる | 素材の性質上、汚れが付きやすい清潔な使用のためには使い捨てを推奨 |
| エラストマー | 素材の耐久性が高く、洗浄による繰り返し使用が可能 | 製品によっては防音効果が十分でないものがある |
| シリコン | 高い耐久性を持ち、長期使用に適している | 装着時の圧力が強く、長時間の使用で耳への負担が大きい |
| 弾性発泡ポリマー | コストパフォーマンスが良く、防音性能も優れている | 適切な使用方法の習得に時間がかかる |
また、フォームタイプ、フランジタイプなどの形状については、使用感を確認してみることが重要です。
遮音性の高さで選ぶ
耳栓を選ぶ際は、遮音性能を示す「NRR値(北米を中心とした規格)」と「SNR値(EUを中心とした規格)」をチェックすることが重要です。これらの値は騒音をどれだけ低減できるかを「dB(デシベル)」で表し、数値が大きいほど遮音性が高くなります。例えば60dBの騒音環境で20dBの遮音性能がある耳栓を使用すると、40dBまで音を抑えられます。工場内(80〜90dB)からホテルの室内(30〜40dB)まで環境によって騒音レベルは異なるため、用途に応じた遮音性能の耳栓を選択することをおすすめします。
耳栓を正しくつける方法
耳栓は正しい方法でつける必要があります。フォームタイプの正しいつけ方は下記のとおりです。
- 耳栓を指でしっかり押しつぶして細長く丸める
- 片手で耳を上後ろ方向に引き上げる
- その状態で耳栓をゆっくり挿入し、約30秒間押さえてふくらむのを待つ
また、フランジタイプの正しいつけ方は次のようになります。
- 耳栓の持ち手部分(軸)をつまむ
- 片手で耳を上後ろ方向に引っ張る
- 3番目のヒレまでを目安に、ゆっくりと回しながら挿入する
正しく耳栓を使うために気をつけたいポイント
正しく耳栓を使うためには、ポイントを押さえておくことが重要です。ここでは2つの大切なポイントを紹介します。
定期的に消毒をして清潔さを保つ
耳栓が清潔でないと耳の中で細菌が繁殖するおそれがあります。フォームタイプは使い捨てが基本なので、衛生的な問題は生じにくいです。一方、フランジタイプは使う度に水洗いをし、デジタルタイプはエタノールなどで拭いておくのがおすすめです。どちらも定期的に消毒をして清潔さを保つよう心がけましょう。
耳に痛みやかゆみなどの違和感を感じたら使用しない
耳に痛み・かゆみなどの違和感を感じるのは、耳栓が合っていないサインです。特に睡眠時は長時間つけ続けるため、耳への負担が大きくなりがちです。その耳栓の使用を中止し、柔らかい素材や小さいサイズ、異なるタイプへの変更を検討しましょう。また、違和感がおさまらなかったり悪化したりする場合は、耳鼻科を受診することをおすすめします。

耳栓は定期的に交換しよう
同じ耳栓を使い続けると、遮音性の低下や破損して耳の中に部品が残るといった問題が起こりやすくなります。そのため、定期的な交換が必要です。交換の目安は素材や形、使用頻度などによっても異なりますが、約2週間とされています。また、他にも次のような交換のタイミングがあるので確認しておきましょう。
- 耳栓が汚れた
- 耳栓が破損した
- 耳栓の形状が崩れた
- 耳栓のふくらむタイミングが早くなった
- 耳栓のふくらむタイミングが遅くなった
まとめ
耳栓は騒音対策や睡眠の質向上に役立つ便利なアイテムですが、正しい使用方法を守ることが重要です。定期的な消毒や交換を行い、清潔に保つことで外耳炎などのリスクを防げます。また、使用目的に合わせて素材や形状を選び、耳に負担をかけないよう注意することで、より安全に活用できます。耳に違和感を感じたら使用を中止し、必要に応じて耳鼻科を受診するなど、適切な対応を心がけましょう。
寝具専門店おすすめのマットレス
NERUSIA高弾性ウレタンマットレス
NERUSIA高弾性ウレタンマットレスは、 硬めのウレタンフォームがしっかりと身体を支えつつ、厚み2cmの中綿入りキルティングカバーによりフィット感のある寝心地を実現したマットレスです。
業界トップクラスの反発力73%の高弾性ウレタンが自然な寝返りをサポートしてくれるため、肩こりや腰痛、寝起きの疲れなどのお悩みをお持ちの方にもおすすめです。
キルティングカバーは夏面(吸汗速乾わた使用)と冬面(吸湿発熱わた使用)に分かれているため、1年中快適にご使用いただけます。防ダニ・抗菌・防臭加工を施しており、耐久性も高く、ロール状に三つ折りが可能など、マットレスに欲しい機能を全て詰め込んだ高品質・高機能マットレスに仕上がっています。圧縮梱包でお届けしますので、搬入の心配もいりません。
雲のやすらぎプレミアムマットレス
「雲のやすらぎプレミアムマットレス」 は「リモートワークで腰痛になった」「寝ても疲れがとれない」などのお悩みのある方におすすめな極厚17cm・5層構造のマットレスです。
まるで浮いているような寝心地の秘密は腰・背中・お尻などの負担を徹底研究してつくられた独自の体圧分散製法。また、夏は通気性・防ダニ・抗菌・防臭、冬は抜群の弾力・保温力・吸収力を発揮してくれるリバーシブル設計で、オールシーズン快適。安心の日本製で、へたりにくさ99.9%も実証済。さらにカバーも取り外して洗える新機能を搭載。
寝具業界では最長水準の100日間の返金保証キャンペーンも実施中。まずは一度試してみてはいかがでしょうか。
NELLマットレス
「NELLマットレス」は「株式会社Morght」と老舗マットレス会社が共同開発したポケットコイルマットレスです。腰部分に硬めのポケットコイルを配置することで睡眠中の自然な寝返りをサポートしてくれるので、寝ている間に体にかかる負荷を軽減してくれます。また、薄いウレタンと不織布を交互に重ねた詰め物を使用ているので、通気性がよく、寝ている間の深部体温を下げ、気持ちのよい眠りを実現してくれます。
商品が到着してから120日のトライアル期間が設けられているのも嬉しいポイントです。特に、マットレスは実際に何日間か試してみないと寝心地などがわからないので、自分に合うマットレスを探している人はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
関連記事
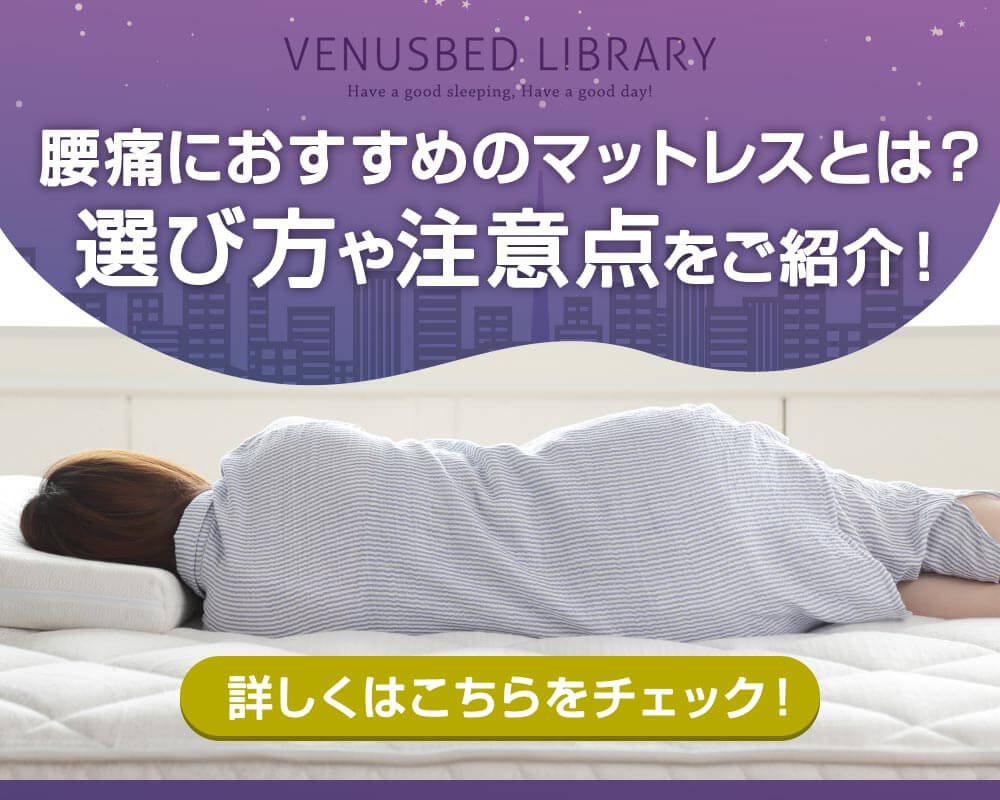

Profile プロフィール
Item カテゴリーで商品を探す
Ranking 人気の記事
New 新着記事
-
シングルベッドを6畳の寝室に2つ置くには?レイアウト例や注意…
-
寝過ぎでだるい!だるさの治し方・原因・予防方法を紹介
-
【眠りが浅い】【夢ばかり見る】熟睡できない原因と対策方法を紹…
-
豆乳は夜寝る前に飲むと美肌につながる!?飲むタイミングによっ…
-
マットレスにカバーは必要?付ける目的やおすすめの商品を紹介
-
掛け布団カバーがずれないようにする方法|ずれにくいカバーの選…



Tags タグで記事を探す